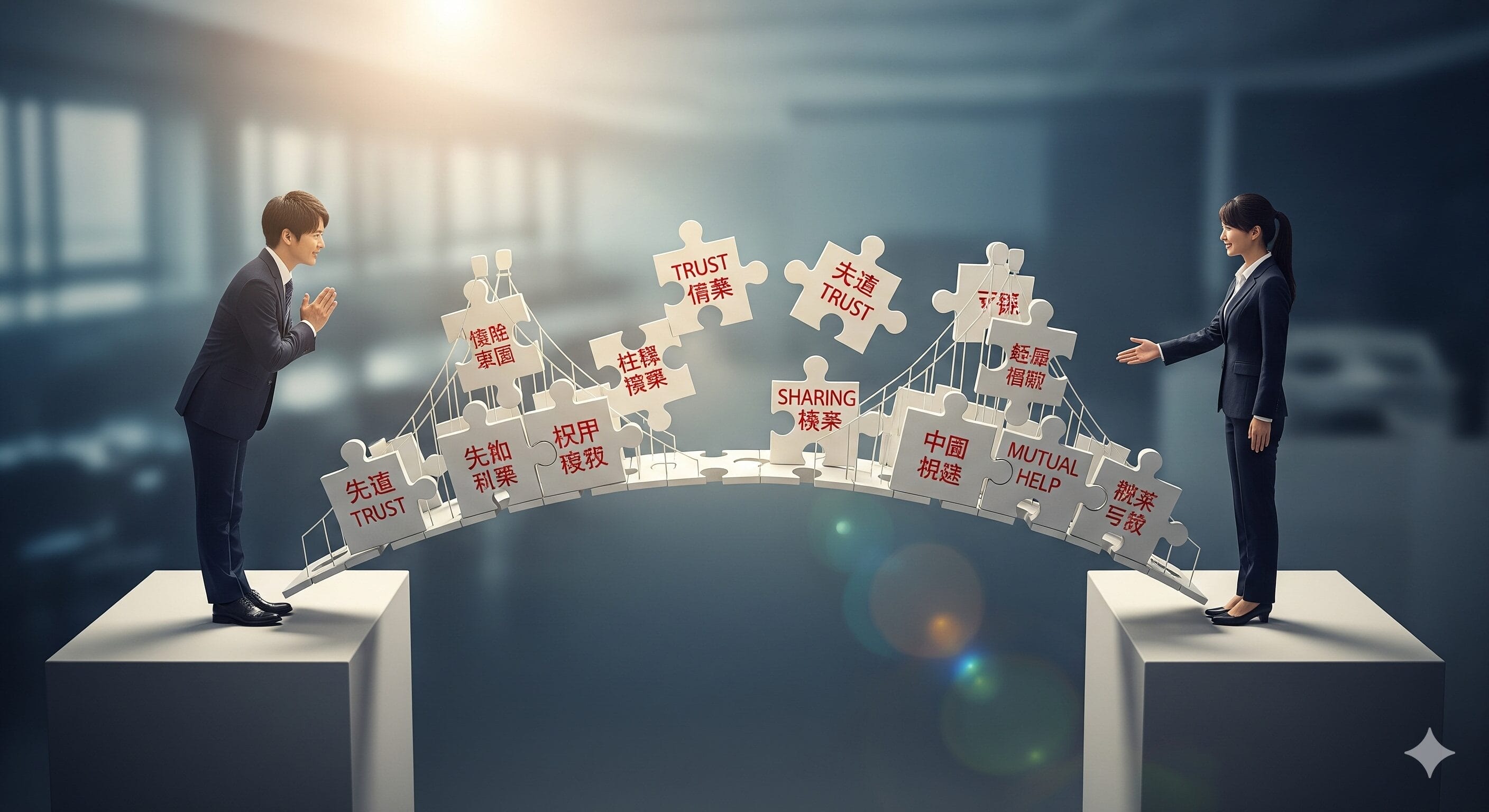日本企業と中国企業。ビジネスの現場で接すると、その組織文化や意思決定プロセス、そして「法令遵守」に対する考え方に大きな違いを感じることがあります。特に日本人ビジネスパーソンの多くが疑問に感じるのが、中国企業における「コンプライアンス」の位置づけではないでしょうか。「中国企業にはコンプライアンスの概念がないのでは?」と感じる声も聞かれます。
しかし、本当にそうなのでしょうか?近年、中国でもコンプライアンスを取り巻く環境は急速に変化しています。この記事では、日本と中国の文化的な背景の違いから、なぜコンプライアンスに対する意識に差が見られるのかを考察し、さらに近年の中国におけるコンプライアンス強化の動きとその実態について詳しく解説します。
なぜ日本企業はコンプライアンスを重視するのか?文化的背景を探る
日本の製品やサービスが高品質で安全であると世界的に評価されている背景には、多くの日本企業がコンプライアンス(法令遵守とその精神)を重視し、厳格に取り組んでいることがあります。では、なぜ日本ではコンプライアンスが根付きやすいのでしょうか?企業努力はもちろんですが、以下のような日本特有の文化的背景が深く関わっていると考えられます。
rìběnrén xǐhuan shāngliáng
1、日本人喜欢商量
日本人は話し合いが大好きrìběnrén xǐhuan guīdìng
2、日本人喜欢规定
日本人は規定を定めるのが大好きrìběnrén kǎolǜ biéren de shì
3、日本人考虑别人的事
日本人は他の人の感情を考慮する
これらの要素が、どのようにコンプライアンス意識と結びついているのか見ていきましょう。
「話し合い」を重んじる文化
島国という地理的条件もあり、日本では古くから限られたコミュニティの中で人々が協力し、調和を保ちながら生きていく必要がありました。そのため、物事を一方的に決めるのではなく、関係者間で十分に「商量」(shāngliáng:話し合い、相談)を行い、合意形成を図る文化が育まれました。
もし、Appleのスティーブ・ジョブズ(史蒂夫·乔布斯:shǐdìfū qiáobùsī)のような、卓越した才能を持つものの、強烈なカリスマ性とトップダウンで物事を進める経営者が日本に現れたとしても、その手法は必ずしも広く受け入れられないかもしれません。個人の強力なリーダーシップよりも、集団での意思決定やプロセスが重視される傾向があるからです。この「話し合い」の文化は、コンプライアンスのルール作りにおいても、関係部署が連携し、慎重に議論を重ねるというプロセスにつながっています。
「規定」を定めることを好む国民性
話し合いを通じて合意に至った事項は、「规定」(guīdìng:規定、ルール)として明文化し、それを組織全体で守っていくことを好む傾向があります。詳細なマニュアルや手順書が作成され、それに沿って業務を進めることで、属人性を排除し、安定した品質や公平性を担保しようとします。
この「規定好き」とも言える性質は、コンプライアンス遵守の基盤となります。社内規則や行動規範が詳細に定められ、社員一人ひとりがそれを理解し、遵守することが求められる環境が、日本企業には整っていると言えるでしょう。

話し合いと合意形成を重視し、ルールを定めることを好む日本の企業文化。
「他者への配慮」と集団主義
「世間体」や「空気を読む」といった言葉に象徴されるように、日本社会では周囲の人々の感情や立場を「考虑」(kǎolǜ:考慮する)し、迷惑をかけないように行動することが美徳とされます。いわゆる「ムラ社会」的な文化の中で、地域社会や組織全体の調和を保つことが重視されてきました。
この「他者への配慮」の精神は、コンプライアンスの目的である「社会的な信頼の維持」「顧客や従業員、地域社会などステークホルダーの保護」「環境保全」といった考え方と親和性が高いと言えます。自分たちの利益だけでなく、社会全体への影響を考え、ルールを守ろうとする意識につながりやすいのです。
日本におけるコンプライアンスの歴史と発展
日本でコンプライアンスが強く意識されるようになった背景には、過去の企業不祥事の経験があります。バブル崩壊後の1990年代から2000年代にかけて、大手企業による品質偽装、不正会計、談合、環境汚染などが相次いで発覚し、社会的な批判が高まりました。これらの事件を教訓に、多くの企業が再発防止策としてコンプライアンス体制の強化に乗り出し、内部統制システムの構築、倫理規定の策定、社員教育の徹底などを進めてきました。
また、会社法改正による内部統制システム構築義務化(大会社等)や、金融商品取引法における内部統制報告制度(J-SOX)の導入なども、企業のコンプライアンス意識向上を後押ししました。こうした法制度の整備と、社会全体の企業を見る目の厳格化が、今日の日本のコンプライアンス重視の姿勢を形作ってきたと言えるでしょう。
中国企業でコンプライアンス遵守が難しいとされる3つの文化的要因
一方、中国では、日本とは異なる文化や価値観が、コンプライアンスに対するアプローチに影響を与えていると考えられます。もちろん、全ての中国企業に当てはまるわけではありませんが、一般的に見られる傾向として以下の点が挙げられます。
qiángdiào gèrén nénglì
1、强调个人能力
個人の能力が強調されるzhǐ bǎohù zìjǐ jiārén hé péngyou
2、只保护自己家人和朋友
自分の家族と友人だけを守るxǐhuan hěn hélǐ de xiǎngfǎ
3、喜欢很合理的想法
合理的な考えを好む
これらの文化的要因が、なぜ中国でコンプライアンス遵守を難しくするのか、具体的に見ていきましょう。
個人の能力と結果を重視する「実力主義」
中国社会では、集団の調和よりも個人の能力や成果が重視される傾向があります。ビジネスにおいても、プロセスよりも結果、特に「赚钱」(zhuànqián:お金儲け)につながるかどうかが最優先される場面が少なくありません。経営トップも強いリーダーシップを発揮し、迅速な意思決定でビジネスチャンスを掴むことが求められます。
このような実力主義、結果主義の環境下では、時にコンプライアンスが「儲け」や「効率」の妨げになると見なされ、後回しにされる可能性があります。ルールを守ることよりも、目標達成や利益確保が優先されるという価値観が根強い場合があるのです。
「関係(グアンシ)」重視と身内意識
中国社会を理解する上で欠かせないのが「关系」(guānxi:グアンシ、コネクション)の存在です。血縁、地縁、学閥などに基づく個人的なつながりが、ビジネスや社会生活において非常に重要な役割を果たします。人々はまず「自己人」(zìjǐrén:身内、仲間)と見なす家族や友人の利益を守ろうとし、それ以外の「外人」(wàirén)に対しては警戒心を持つ傾向があります。
この「身内意識」は、時に「法律や規則よりも人間関係が優先される」状況を生み出すことがあります。「このくらいなら身内だから大丈夫だろう」「あの人との関係があるから融通を利かせよう」といった判断が、コンプライアンス違反につながるリスクを孕んでいます。また、「自分たちに関係のない他者や、漠然とした社会全体の安全・環境」への配慮は、身内への配慮に比べて優先度が低くなりがちです。
徹底した「合理主義」の功罪
中国の人々は非常に現実的で「合理」(hélǐ)的な考え方を好むと言われます。これは、無駄を嫌い、効率を追求するという点でビジネス上の強みにもなりますが、コンプライアンスの観点からは課題となる側面もあります。
例えば、記事中の例にあるように、誰も見ていない状況で形式的なルールを守ることに意味を見出さない、という考え方です。「横断歩道で指差し確認をする」「床に落ちた食品を廃棄する」といったルールが定められていても、「誰も見ていないし、実質的な問題もない(見つからなければ損はしない)」と判断すれば、それを守らない可能性が出てきます。ルールそのものの意義や目的よりも、「守らなかった場合のリスク(罰則や発覚の可能性)」と「守らなかった場合のメリット(手間やコストの削減)」を天秤にかける、極めて合理的な(あるいは功利的な)判断がなされやすいのです。

個人の能力、関係性、合理性が重視される中国のビジネス文化。
トップダウン文化の影響
多くの中国企業では、意思決定がトップダウンで行われる傾向が強いです。経営トップの意向が絶対的な影響力を持ち、現場の意見が反映されにくい構造になっている場合があります。もし経営トップがコンプライアンスよりも短期的な利益や成長を優先する姿勢であれば、組織全体としてコンプライアンス意識が希薄になる可能性があります。
逆に言えば、経営トップが強い意志を持ってコンプライアンス遵守を掲げれば、組織全体に浸透しやすいという側面もあります。近年の中国におけるコンプライアンス強化の動きは、まさにこのトップダウン(国家レベルでの指導)が大きく影響しています。
コンプライアンスは「上から」?国家指導による変化の実態
利益第一、合理主義、トップダウンといった文化的な背景から、企業が自発的に厳格なコンプライアンス体制を築くのは容易ではない面がありました。しかし、ここ数年、特に環境問題を中心に、中国企業のコンプライアンスへの取り組みは急速に進展しています。その最大の推進力となっているのが、中国政府による強力な指導と規制強化です。
環境規制強化の背景と効果
深刻な大気汚染や水質汚染、土壌汚染などの環境問題は、国民の健康を脅かし、社会不安を引き起こす要因となっていました。これに対し、習近平政権は「緑水青山就是金山銀山(緑の山河は金山・銀山)」のスローガンの下、環境保護を最重要課題の一つと位置づけ、規制を大幅に強化しました。
国家環境保護総局(現在は生態環境部に再編)などの政府機関が、工場への立ち入り検査(环保督察:huánbǎo dūchá)を厳格化し、排出基準違反や汚染物質の不法投棄に対して厳しい罰則を科すようになりました。これにより、多くの企業が対応を迫られ、大気汚染物質の削減、廃水処理設備の導入、廃棄物の分別・リサイクルなどに本格的に取り組み始めました。
罰金制度と企業の対応
政府の規制強化を実効性あらしめているのが、高額な「罚金」(fájīn:罰金)制度です。「1年以内に改善が見られなければ操業停止、あるいは巨額の罰金を科す」といった厳しい措置が取られるようになり、これまで環境対策に消極的だった企業も、国家には逆らえないと判断し、コストをかけてでも対策を講じるようになりました。まさに「上に政策あれば下に対策あり」という状況ですが、結果として環境関連のコンプライアンスは着実に進展しています。
環境以外の分野でのコンプライアンス動向(労働法、独禁法など)
政府主導のコンプライアンス強化の動きは、環境分野に限りません。
- 労働法規: 労働者の権利保護意識の高まりを受け、労働契約、労働時間、残業代未払い、社会保険などに関する法執行が強化される傾向にあります。特に外資系企業はターゲットにされやすいため、注意が必要です。
- 独占禁止法: ITプラットフォーマーなどを中心に、市場支配的地位の濫用や不公正な取引慣行に対する取り締まりが強化されています。
- データセキュリティ・個人情報保護: サイバーセキュリティ法、データセキュリティ法、個人情報保護法といった法律が相次いで施行され、データの越境移転や個人情報の取り扱いに関する規制が厳格化されています。
- 知的財産権保護: 模倣品対策など、知的財産権の保護も強化される方向性にあります。
- 汚職・腐敗防止: 政府は引き続き汚職・腐敗に対する厳しい姿勢を示しており、企業に対しても贈収賄防止に関するコンプライアンス体制の整備を求めています。
これらの分野においても、法制度の整備と法執行の強化が進んでおり、企業は幅広い分野でコンプライアンスリスクに対応する必要に迫られています。
中国企業のコンプライアンス、今後の展望と課題
国家主導で進められてきた中国のコンプライアンス強化ですが、今後はどのような方向に進むのでしょうか?いくつかの変化の兆しと課題が見られます。
グローバル化と意識の変化の兆し
中国企業の海外進出や、グローバルサプライチェーンへの参画が進む中で、国際的な基準やルールに合わせたコンプライアンス体制の必要性を認識する企業が増えています。海外の取引先や投資家から、人権、環境、ガバナンス(ESG)への配慮を求められるケースも増えており、これが企業自身の意識改革を促す要因となっています。
若い世代の価値観の変化
高等教育を受け、海外経験を持つ若い世代の間では、環境問題や社会貢献、労働者の権利などに対する意識が高まっています。彼らが企業の中心的な役割を担うようになるにつれて、企業文化やコンプライアンスに対する考え方も変化していく可能性があります。
法制度整備と執行の課題
法制度の整備は急速に進んでいますが、その運用や解釈が不明確な部分も多く、法執行の透明性や公平性にも課題が残ります。また、中央政府の方針と地方政府の運用に温度差が見られることもあります。企業にとっては、常に最新の法規制動向を把握し、予期せぬリスクに備える必要があり、専門家のアドバイスが不可欠となる場面も多いでしょう。
日系企業が注意すべき点
中国で事業を展開する日系企業にとっては、日本の本社基準のコンプライアンスを徹底することはもちろん、中国特有の法規制や商慣習、文化的背景を深く理解し、それに合わせた対策を講じることが不可欠です。特に、労働法規、データ関連法規、環境規制、贈収賄防止などは重点的に対応すべき分野です。安易な「グアンシ」頼みのビジネスや、現地の慣習だからと安易に妥協することは、大きなリスクにつながる可能性があります。
まとめ:文化の違いを理解し、変化を見据える
「中国企業にコンプライアンス意識がない」というのは、もはや過去のイメージになりつつあります。確かに、日本とは異なる文化的背景から、コンプライアンスに対するアプローチや優先順位に違いが見られるのは事実です。しかし、特に政府主導による規制強化と、グローバル化の進展により、中国企業のコンプライアンスを取り巻く環境は大きく変化しています。
日本と中国の国民性や文化の違いを理解し、一方的な見方で判断するのではなく、それぞれの背景にある理由を探ることが、異文化理解の第一歩です。そして、変化の激しい中国のビジネス環境においては、常に最新の情報を把握し、その変化に対応していく柔軟な姿勢が求められます。
[s_ad]