藤井聡太八冠の活躍により、空前のブームに沸く日本の将棋界。その奥深い戦略性に魅了されるファンは後を絶ちません。しかし、日本の将棋がニュースで大きく報じられる一方、お隣の中国ではほとんど話題にならないことをご存知でしょうか?その理由は、中国にはるか昔から国民に愛され続ける「もう一つの将棋」が存在するからです。それが「象棋(xiàngqí / シャンチー)」。今回は、日本の将棋ファンはもちろん、中国文化に興味を持つすべての方に向けて、二つの将棋が持つ知られざる共通点と、文化や歴史を色濃く反映した決定的な違いを、ルールから駒の動き、文化的背景に至るまで徹底的に解説します。この記事を読み終える頃には、あなたもシャンチーの虜になっているかもしれません。ゲームのルールを通じて異文化を学ぶことは、言葉の壁を越えたコミュニケーションの第一歩です。より深く中国を知りたくなったら、中国語教室で言葉の世界に飛び込んでみるのも素晴らしい選択肢でしょう。
日本将棋と中国象棋、その知られざる関係とは?
見た目もルールも異なる二つの将棋ですが、その源流を遡ると、驚くべき共通の祖先にたどり着きます。両者の関係は、まさに「遠い親戚」と呼ぶにふさわしいものです。
共通の祖先、古代インドの「チャトランガ」
日本将棋と中国象棋、そして西洋のチェス。これら世界三大将棋の共通の祖先と考えられているのが、4世紀から6世紀頃の古代インドで生まれた盤上ゲーム「チャトランガ」です。サンスクリット語で「4つの部門」を意味するこのゲームは、当時のインド軍を構成した「歩兵、騎兵、象兵、戦車」の4つの兵科を駒としていました。初期のチャトランガは4人制で、サイコロの目に従って駒を動かすという、偶然性の要素も含まれていたとされています。
この画期的なゲームが、交易路シルクロードなどを通じて世界各地へ伝播していきました。東南アジアや東アジアに伝わる過程で仏教の影響を受けながら変容し、中国では象棋、朝鮮半島ではチャンギ、そして日本では将棋へと姿を変えていきました。一方、ペルシャを経て西へ伝わったものは、チェスとしてヨーロッパ全土に広まりました。一つのゲームが、各地域の文化や価値観を取り込みながら、全く異なる魅力を持つゲームへと進化していった歴史は、まさに壮大な文化の旅路と言えるでしょう。
盤上の宇宙観 – それぞれの文化が反映されたゲーム性
二つの将棋は、その盤面や駒にそれぞれの国の歴史観や世界観を色濃く反映しています。日本の将棋が、玉将を中心とした「宮中の序列」や、敵味方が入り乱れて戦う「武士の合戦」をモチーフにしているのに対し、中国象棋の盤面は、古代中国の一大叙事詩である「楚漢戦争」をテーマにしています。
盤の中央を横切る一本の線には「楚河漢界」と書かれています。これは、項羽が率いる「楚」と、劉邦が率いる「漢」が、長きにわたり天下を争った際に両軍を隔てた広武山の渓谷を象徴しています。プレイヤーは楚の項羽(黒側)か漢の劉邦(赤側)となり、盤上で再び天下統一を争うのです。このように、ゲームの背景にあるストーリーを知ることで、駒の一つ一つに込められた意味合いがより深く理解できます。
【徹底比較】盤面と駒から見る日本将棋と中国象棋の7つの違い
ここからは、二つの将棋の具体的な違いを7つのポイントに分けて、可能な限り詳しく解説していきます。日本将棋の知識がある方なら、その違いの面白さにきっと引き込まれるはずです。
① 盤の構造:「河」と「九宮」が支配する戦場
まず、戦いの舞台となる盤の構造が全く異なります。日本の将棋が9×9のマス目の中に駒を置くのに対し、中国象棋は縦10本、横9本の線で構成され、駒はマスの中ではなく線の交点に置きます。これにより、盤上の交点の数は90となります。
- 楚河漢界(河):盤の中央には「河」と呼ばれる空白地帯があり、これが盤面を二つの陣地に分けています。この河は、一部の駒の動きを制限する重要な役割を果たします。
- 九宮(きゅうきゅう):各陣地の中央(上から3段、横3列)には、斜めの線が引かれた「九宮」と呼ばれる特別なエリアが存在します。これは王が守られるべき「城」や「宮殿」を意味し、最も重要な駒である「帥(将)」と、それを守る「士」はこの九宮の中から出ることができません。

「河」と「九宮」の存在が、象棋の戦略を日本将棋とは全く異なるものにしている。
② 駒の種類と配置:両軍の戦力が全く異なる
駒の種類は、日本将棋が8種類(玉、飛、角、金、銀、桂、香、歩)であるのに対し、中国象棋は7種類です。日本の金・銀・桂・香に相当する駒はなく、代わりに象棋独自の駒が存在します。
③ 駒の動き:似ているようで全く違う個性的な駒たち
ここが最も面白い部分です。各駒の動きを、日本将棋の駒と比較しながら見ていきましょう。
-
帥 (shuài) / 将 (jiàng) – 日本の王将・玉将
最も重要な駒。取られたら負けです。縦横に1マスずつ動けますが、九宮から出ることはできません。 -
士 (shì) / 仕 (shì) – 独自の駒
帥(将)を護衛する駒。九宮内の斜め線に沿って1マスだけ動けます。九宮から出ることはできません。 -
象 (xiàng) / 相 (xiàng) – 独自の駒
斜め(田の字の対角線)に2マス動きます。ただし、河を渡ることはできず、自陣を守ることに特化しています。また、進路上(田の字の中心)に他の駒があると、その方向に進むことはできません(これを「塞象眼(そくそうがん)」と言います)。 -
馬 (mǎ) / 傌 (mà) – 日本の桂馬に似ている
八方桂馬のように、縦か横に1マス進んだ後、その先の斜め方向に1マス進みます。日本の桂馬と違い、前後左右どこへでも進めます。しかし、弱点があり、縦か横の進路上に他の駒があると、その方向には進めません(これを「蹩馬腿(べつばたい)」と言います)。 -
車 (jū) / 俥 (jū) – 日本の飛車
日本の飛車と全く同じ動きです。縦横に好きなだけ進めます。象棋においても最強の攻撃力を誇ります。 -
炮 (pào) / 砲 (pào) – 象棋を象徴する駒
象棋で最もユニークで、戦略の鍵を握る駒。動くだけの場合は車と同じですが、駒を取る時だけは、自分と相手の駒の間に、駒を一つだけ飛び越えなければなりません(これを「跳駒」と言います)。この駒の存在により、遠距離からの奇襲や複雑なコンビネーションが生まれます。 -
兵 (bīng) / 卒 (zú) – 日本の歩兵
前に1マスだけ進みます。日本の「と金」のように成ることはありません。ただし、一度河を渡って敵陣に入ると、前に加えて左右にも1マスずつ進めるようになります。それでも後ろに戻ることはできません。
④ 最大の違い:「持ち駒」ルールの有無
日本将棋の最大の特徴であり、ゲームを無限に複雑にしているのが「取った駒を自分の戦力として再利用できる(持ち駒)」ルールです。これにより、終盤になっても盤上の駒が減らず、一瞬の油断が大逆転につながるスリリングな展開が生まれます。しかし、中国象棋はチェスと同様、一度取られた駒は盤上から完全に取り除かれ、二度と使うことはできません。このルールにより、象棋は駒が減っていく引き算のゲームとなります。中盤以降は、いかに駒損をせず、有利な交換を進めていくかという純粋な計算力と大局観がより重要になります。
⑤ 王のルール:「王見王(ワンジャンワン)」の禁じ手
象棋には、日本将棋にはない王に関する絶対的な禁じ手が存在します。それが「王見王(対面)」です。これは、自軍の帥(将)と敵軍の将(帥)が、盤上の同じ縦のライン上で、間に他の駒が一つもない状態で直接向かい合ってはならないというルールです。もし相手が動かした結果この形になった場合、その時点で相手の勝ちとなります。逆に、自分が動かした結果この形になると、即座に反則負けです。このルールは終盤戦で特に重要になり、相手の王の逃げ道を塞いだり、自陣の駒を動かす際の制約になったりします。
⑥ 駒の表記とデザイン:文化を映す形
駒そのもののデザインも大きく異なります。日本の将棋駒が黄楊などの木材から作られた五角形で、駒の動きを直感的に示す形をしているのに対し、中国象棋の駒は円盤状(円柱)です。色は赤と黒(または緑や青)に分かれており、駒の種類は表面に書かれた漢字で区別します。この平面的でシンプルな駒のデザインは、屋外の石のテーブルなど、どんな場所でも気軽に楽しめる象棋の大衆性を象徴しているとも言えます。
⑦ 引き分け(和棋)の規定
日本将棋では「千日手」や「持将棋」といった特殊な状況でしか引き分けになりませんが、中国象棋では引き分け(和棋 / héqí)がより頻繁に発生します。例えば、どちらの側も相手を詰ます有効な攻め駒がなくなった場合や、同じ局面が繰り返し現れ、両者が手を変えない場合(長将、長捉などの反則規定あり)などは、審判の判断や両者の合意により引き分けとなります。持ち駒がないため、終盤は戦力が枯渇しやすく、引き分けで終わる対局も少なくありません。
中国語で将棋を語る!覚えておきたい単語と表現
中国人と象棋を通じて交流する際に役立つ、基本的な中国語表現を学びましょう。適切な動詞の選択など、面白い発見があります。
「将棋を指す」はなぜ “下象棋” なのか?
日本語では「将棋を指す」と言いますが、中国語ではどう表現するのでしょうか。最も適切な動詞は「下 (xià)」です。
下象棋 (xià xiàngqí) – 将棋を指す
この「下」という動詞は、象棋だけでなく囲碁(下围棋 / xià wéiqí)など、他の多くの盤上ゲームで共通して使われます。これは、盤面に対して上から駒を「下ろす」「置く」という動作のイメージから来ています。日本語の「指す」という表現の繊細さとはまた違った、面白い文化の違いが感じられます。
覚えておくと便利なフレーズ集
対局中にこれらのフレーズを使えば、きっと相手との距離が縮まるはずです。
- 「你会下象棋吗?」 (nǐ huì xià xiàngqí ma?) – あなたはシャンチーができますか?
- 「将军!」 (jiāngjūn!) – 王手! (チェック!)
- 「死棋了。」 (sǐqí le) – 詰みです。(チェックメイト。)
- 「该你了 / 你走一步。」 (gāi nǐ le / nǐ zǒu yí bù) – あなたの番ですよ。
- 「这步棋很高明!」 (zhè bù qí hěn gāomíng!) – その一手は見事ですね!
- 「我们和棋吧。」 (wǒmen héqí ba) – 引き分けにしましょう。
- 「我没下过日本象棋。」 (wǒ méi xià guò Rìběn xiàngqí) – 日本の将棋は指したことがありません。
中国の路上将棋文化:公園の賭け将棋に挑戦?
中国の象棋文化を語る上で欠かせないのが、路上で繰り広げられる庶民の将棋風景です。
公園の日常風景としての「象棋角」
中国の都市部の公園を散策していると、ほぼ必ずと言っていいほど、高齢者たちが集まって象棋に興じている一角に出会います。ここは「象棋角(シャンチーコーナー)」と呼ばれ、退職した男性たちにとって最も重要な社交の場の一つとなっています。対局者だけでなく、その周りには常に何重もの人だかりができ、一手一手にヤジや賞賛が飛び交います。言葉は通じなくても、その熱気と楽しげな雰囲気は、象棋が中国の庶民の生活にいかに深く根付いているかを物語っています。

公園の「象棋角」は、中国の高齢者にとって重要な社交と娯楽の場である。
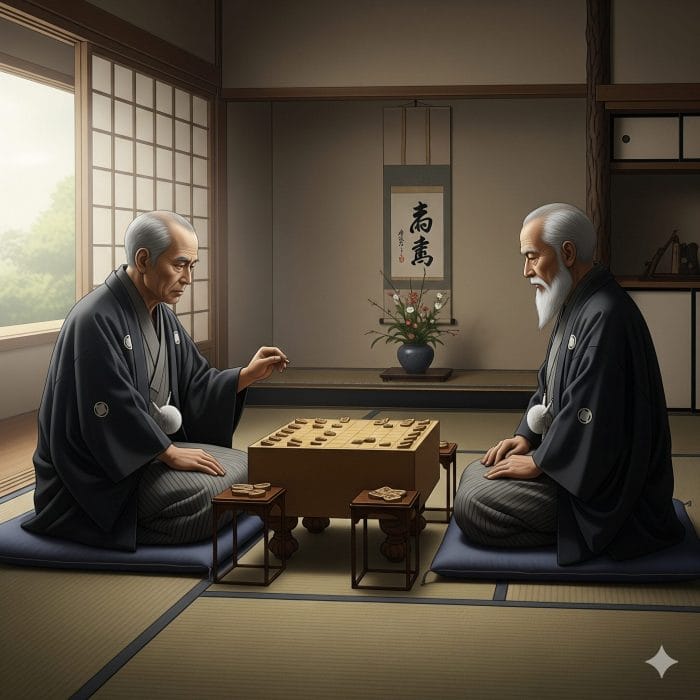
静寂と緊張感が漂う日本将棋の対局は、中国の路上将棋とは対照的な文化を示す。
賭け将棋(残局)の巧妙な罠
一方で、観光客が賑わう歩道などで見かける路上将棋には注意が必要です。地面に布製の盤を広げ、数個の駒を並べて「この局面で私に勝てたら賞金を払う」と通行人に挑戦を促している光景です。これは「残局(cánjú)」と呼ばれる終盤の詰めシャンチーで、多くの場合、賭けが行われています。
一見すると、挑戦者側(多くは赤側)が圧倒的に有利で、簡単に勝てそうに見えます。しかし、これらはプロの棋士が何日もかけて考案した、極めて難解な詰めシャンチーのパズルです。素人が少し考えた程度で見える勝ち筋には、必ず巧妙な罠や落とし穴が仕掛けられており、挑戦してもまず勝つことはできません。周りで囃し立てている野次馬も、実は仲間(サクラ)であることがほとんどです。これは一種の「詰将棋詐欺」に近いもので、観光客がお金を稼ぐ手段にはなり得ません。中国の路上文化として遠巻きに眺めるに留め、安易に挑戦しないのが賢明です。
まとめ
日本将棋と中国象棋(シャンチー)は、同じ祖先を持ちながらも、全く異なる進化を遂げた、魅力的な盤上ゲームです。取った駒を再利用し、複雑で逆転の妙が楽しめる日本将棋。そして、河や九宮といった独特の盤面で、駒が減っていく中で純粋な計算力と戦略が試される中国象棋。どちらが優れているということではなく、それぞれが自国の歴史や文化を色濃く反映した、奥深い世界を持っています。もしあなたが日本将棋のファンなら、シャンチーのルールを覚えるのはそれほど難しくありません。言葉が通じなくても、盤を挟めば世界中の人々と対話ができる。シャンチーを学ぶことは、中国文化への理解を深め、新たな友人を作るための最高のきっかけになるかもしれません。さあ、あなたもこの奥深い盤上の宇宙に、一歩足を踏み入れてみませんか?



