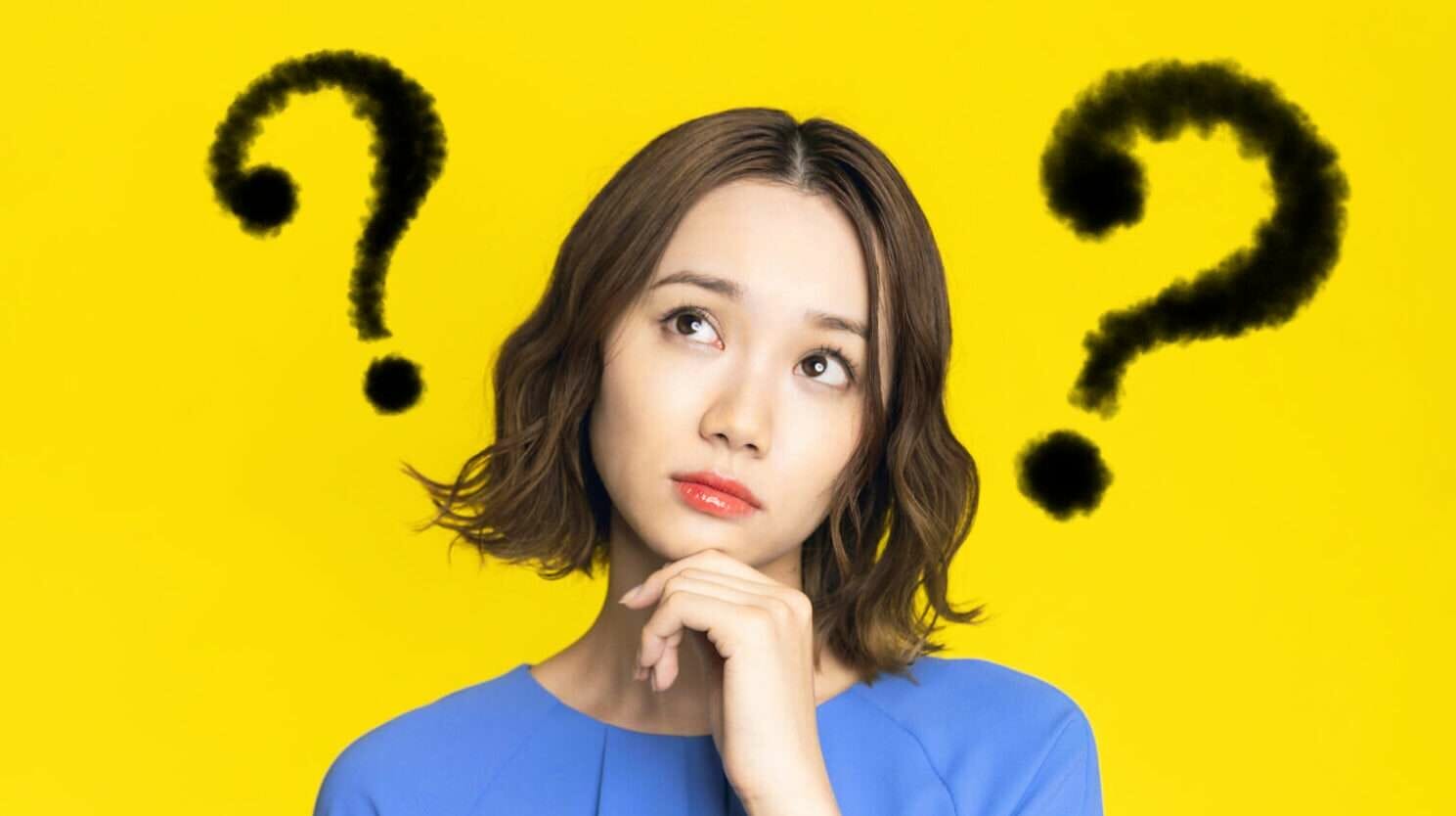中国語の学習を始めると、早い段階で「你好 (nǐ hǎo)」などの基本的な挨拶表現に触れます。しかし、学習が進むにつれて、「もっと自然な言い方はないかな?」「時間帯に合わせた挨拶はどうすればいいの?」「特に夜の挨拶、『こんばんは』って中国語で何て言うんだろう?」といった疑問が湧いてくるのではないでしょうか。さらに、中国大陸と台湾では言葉遣いに違いがあることも知られており、「こんばんは」の表現も異なるのか気になるところです。
この記事では、そうした疑問に答えるべく、中国語と台湾華語における「こんばんは」の表現を徹底比較します。教科書で習う基本形から、実際の会話でよく使われるネイティブ表現、さらには時間帯に縛られない便利な挨拶フレーズまで、具体的な使い方や文化的背景を交えながら詳しくご紹介します。これを読めば、中国大陸でも台湾でも、自信を持って自然な挨拶ができるようになるはずです!
中国語の「こんばんは」:基本とネイティブの使い方
まずは、中国大陸で主に使われる普通話(標準中国語)における「こんばんは」の表現について見ていきましょう。日本語と同じように、夜の時間帯に使う挨拶が存在しますが、その使われ方には少し注意が必要です。
教科書で習う「晚上好 (wǎnshàng hǎo)」- こんばんは
中国語の教科書で「こんばんは」として紹介されている最も一般的な表現は「晚上好 (wǎnshàng hǎo)」です。分解してみると、晚上 (wǎnshàng) が「夜、晩」(通常、日没後から深夜0時頃までを指す)を意味し、好 (hǎo) が「良い、こんにちは」といった挨拶の要素を表します。つまり、直訳すると「夜よ、こんにちは」となり、日本語の「こんばんは」に相当する時間帯の挨拶であることがわかります。
同じ構造で、「おはようございます」は「早上好 (zǎoshang hǎo)」(早上 = 朝)、「こんにちは」は「下午好 (xiàwǔ hǎo)」(下午 = 午後)となります。このように、時間帯を表す言葉に「好」をつけることで、その時間帯の挨拶になる、という基本的なルールは理解しやすいでしょう。
wǎnshàng hǎo
晚上好
こんばんは
「晚上好」はいつ使う?実は日常会話では稀な理由
教科書では基本の挨拶として習う「晚上好」ですが、驚くべきことに、実際の中国人の日常会話ではほとんど使われません。もし、友人や同僚、家族など、親しい間柄の相手に対して「晚上好」と挨拶したら、相手は少し驚いて、「どうしてそんなに丁寧なの?」「何かあったの?」と、よそよそしい、あるいは改まった印象を受けてしまう可能性が高いです。
これはなぜでしょうか?理由としては、中国文化における人間関係の捉え方が関係していると考えられます。日本では「親しき仲にも礼儀あり」という考え方が重視され、親しい相手にも丁寧な言葉遣いをすることが美徳とされる場面があります。一方、中国では、特に親しい間柄においては、「不见外 (bú jiànwài)」つまり「他人行儀にしない」「水臭いことはしない」ことが、親密さの証とされる傾向があります。「晚上好」のような丁寧すぎる挨拶は、かえって相手との間に壁を作ってしまう、距離を感じさせてしまうと受け取られかねないのです。
もちろん、これはあくまで一般的な傾向であり、個人差や状況にもよります。しかし、ネイティブスピーカーが日常的に使う挨拶ではない、という点はしっかり覚えておく必要があります。
フォーマルな場面やメディアでの「晚上好」
では、「晚上好」は全く使われないのかというと、そうではありません。日常会話では稀ですが、フォーマルな場面や公の場では、適切な挨拶として使われます。具体的には、以下のような場面で耳にする機会があります。
- 公式なスピーチやプレゼンテーションの冒頭:会議、講演会、祝賀会などで、聴衆に対して「女士们,先生们,晚上好! (Nǚshìmen, xiānshengmen, wǎnshàng hǎo! – 紳士淑女の皆様、こんばんは!)」のように挨拶します。
- テレビやラジオのニュース番組、公式イベント:キャスターや司会者が視聴者・聴衆に対して呼びかける際に使われます。例:「各位观众/听众,晚上好! (Gèwèi guānzhòng/tīngzhòng, wǎnshàng hǎo! – 視聴者/リスナーの皆さん、こんばんは!)」
- ホテルや高級レストランなど、格式の高いサービス業:スタッフがお客様に対して丁寧な挨拶として使うことがあります。
このように、「晚上好」は、不特定多数の相手や、敬意を払うべき相手に対して、改まった場で使われる「公的な挨拶」としての性格が強いと言えます。ニュースや公式なスピーチを聞く際には、どのようなトーンで、どのような文脈で「晚上好」が使われているかに注目してみると、そのニュアンスがより掴めるでしょう。

「晚上好」はスピーチなどフォーマルな場面で使われます
「こんばんは」だけじゃない!夜の挨拶いろいろ
日常会話で「晚上好」を使わないとなると、夜に人と会ったり、別れたりする際には、どのように挨拶すれば良いのでしょうか?状況に応じた、より自然な夜の挨拶表現を見ていきましょう。
「おやすみなさい」関連の表現 (晚安, 睡个好觉 など)
夜、寝る前の挨拶としては、以下のような表現がよく使われます。これらは比較的親しい間柄で使うのが一般的です。
wǎn’ān
晚安
おやすみなさい (やや丁寧、書き言葉でも使われる)
shuì gè hǎo jiào
睡个好觉
ぐっすり寝てね / よくお休み (親しい相手に)
zuò ge hǎo mèng
做个好梦
良い夢を見てね! (親しい相手、特に子供や恋人に)
hǎohāor shuì ba
好好儿睡吧
しっかり寝てね / ゆっくりお休み (相手を気遣う)
これらの表現は、WeChatなどのメッセージアプリや電話での会話の締めくくりにもよく使われます。「晚安」は少し丁寧な響きがありますが、親しい間でも使われます。他の表現はより口語的で、温かい気持ちを伝えるニュアンスがあります。
夜の気軽な声かけ・別れ際の挨拶
夜の時間帯に友人や知人に会った場合、特別な夜の挨拶をするというよりは、時間帯に関係なく使えるカジュアルな挨拶(後述する「嗨(hāi)」や「哈喽(hā lou)」など)を使うか、あるいは挨拶なしにいきなり「来了!(Lái le!) – 来たね!」「在忙什么呢?(Zài máng shénme ne?) – 何してるの?/忙しいの?」のように声をかけることも多いです。
夜に別れる際には、「おやすみ」系の挨拶の他に、以下のような表現も使われます。
zǎo diǎn xiūxi (ba)
早点休息(吧)
早く休んでね (相手を気遣う)
míngtiān jiàn
明天见
また明日 (明日も会う予定がある場合)
wǒ xiān zǒu le
我先走了
お先に失礼します / 先に帰るね
báibái / bàibài
白白 / 拜拜
バイバイ (英語の Bye Bye から)
このように、夜特有の挨拶にこだわるよりも、状況や相手との関係性に合わせて、より自然で一般的な表現を使うのが中国語のコミュニケーションスタイルと言えるでしょう。
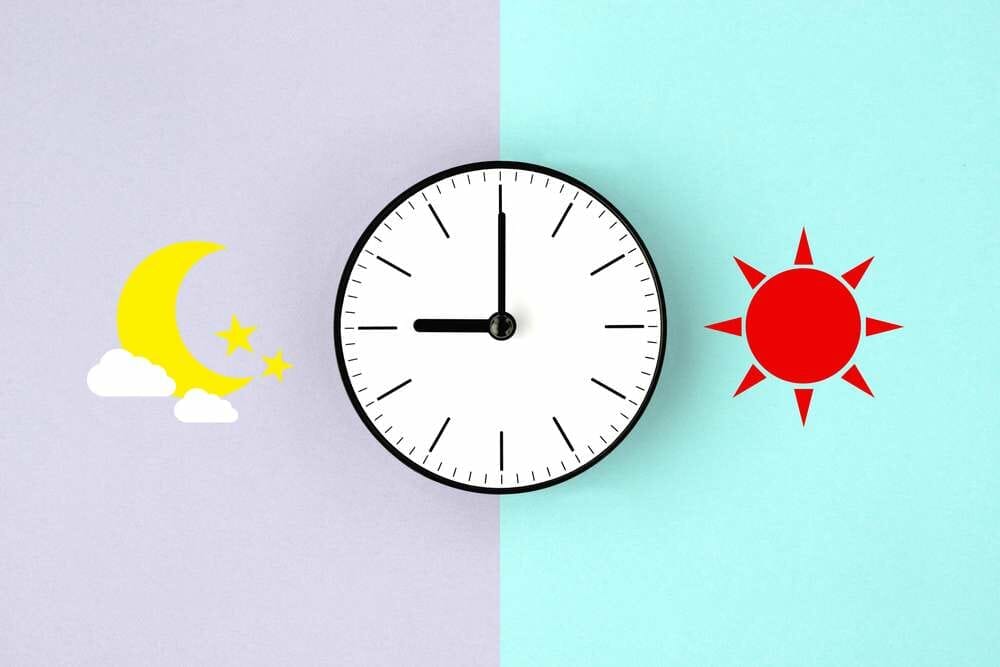
「晚安」は中国大陸では「おやすみ」の意味で使われます
台湾華語の「こんばんは」と挨拶の特徴
次に、台湾で話されている中国語(台湾華語、國語)における夜の挨拶について見ていきましょう。中国大陸の普通話とは、発音や語彙、表現習慣にいくつか違いがあり、「こんばんは」の言い方にも特徴が見られます。
台湾では「晚安 (wǎn’ān)」が「こんばんは」?
台湾では、夜の時間帯の挨拶として「晚安 (wǎn’ān)」が使われることがあります。中国大陸では「晚安」は基本的に「おやすみなさい」の意味で使われるため、これは大きな違いです。台湾を訪れた際に、夜店の人やホテルのスタッフから「晚安!」と声をかけられて、「もう寝る時間なのかな?」と戸惑った経験がある人もいるかもしれません。
もちろん、台湾でも中国大陸と同じ「晚上好 (wǎnshàng hǎo)」が全く通じないわけではありません。特に標準的な教育を受けた若い世代や、フォーマルな場面では理解されます。しかし、日常的な場面、特に年配の方や地方などでは、「晚安」の方がより自然な「こんばんは」として使われる傾向があるようです。また、台湾語(閩南語)の影響を受けている可能性も指摘されています。
「晚安」の二つの意味:「こんばんは」と「おやすみなさい」
তাহলে কি তাইওয়ানে “晚安” এর অর্থ কেবল “শুভ সন্ধ্যা”? না, ব্যাপারটা অতটা সোজাসাপ্টা নয়। তাইওয়ানেও “晚安” শব্দটি “শুভ রাত্রি” বা ঘুমাতে যাওয়ার আগের বিদায় সম্ভাষণ হিসেবেও বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়।
つまり、台湾における「晚安」は、文脈によって「こんばんは」とも「おやすみなさい」とも解釈されうる、少し曖昧さを持った言葉なのです。具体的にどちらの意味で使われているかは、会話の流れや状況(夜に会ったばかりなのか、別れ際なのか、寝る前の挨拶なのかなど)から判断する必要があります。台湾の人々も、この二つの意味を明確に区別せずに、夜の時間帯の挨拶として柔軟に使っている側面があるようです。
台湾でも基本は「你好 (Nǐ hǎo / Lí hó)」だけど…
台湾でも、時間帯に関わらず使える最も基本的な挨拶は「你好」です。発音は、標準中国語(普通話)と同じ「Nǐ hǎo (ニーハオ)」ですが、台湾語(閩南語)の影響を受けた発音「Lí hó (リーホー / リィホー)」も広く使われており、特に親しみを込めた場面や年配の方との会話で耳にすることがあります。
lí hó (台湾語発音)
你好
こんにちは/はじめまして
台湾では、街中で「你好!你好!」と繰り返して挨拶する場面をよく見かけます。単語を繰り返すことで、柔らかく親しみやすい印象を与える効果があります。
ただし、中国大陸と同様に、台湾でも非常に親しい友人や家族に対して「你好」を使うことは稀です。どちらかというと、初対面の相手に対する「はじめまして」の意味合いや、店員がお客さんに使うような、ある程度の距離感を保った丁寧な挨拶、あるいは公的な場面での挨拶として使われることが多いようです。「你好」は、やはり少し「礼儀正しい」「かしこまった」ニュアンスを持つ言葉として認識されています。
台湾ならでは!知っておきたい挨拶・便利フレーズ
台湾華語や台湾語に由来する、台湾でよく使われる独特の挨拶や便利なフレーズもいくつかご紹介します。これらを使えると、台湾の人々との距離が一気に縮まるかもしれません。
早安 (zǎo’ān) – おはよう
zǎo ān
早安
おはよう
「こんばんは」の「晚安」と同様に、朝の挨拶も「早上好 (zǎoshang hǎo)」ではなく「早安 (zǎo’ān)」を使うのが台湾では一般的です。「早安!」と元気に挨拶してみましょう。
多謝 (duō xiè) – ありがとう
duō xiè
多謝
ありがとう / どうも (感謝の度合いがやや強い場合や、贈り物へのお礼など)
台湾では「ありがとう」として「謝謝 (xièxie)」(普通話と同じ)ももちろん使いますが、「多謝 (duō xiè)」も非常によく使われます。特に、贈り物をもらった時や、少し丁寧にお礼を言いたい場面などで使われることが多いようです。「多くの感謝」という文字通りの意味が伝わる表現です。
不會 (bú huì) – どういたしまして
bú huì
不會
どういたしまして / いいえ、そんなことないです
中国大陸で「不会 (bú huì)」は主に「~できない」「~のはずがない」という意味で使われますが、台湾では「ありがとう(謝謝、多謝)」に対する返答として「どういたしまして」の意味で非常によく使われます。(大陸で「どういたしまして」は「不客气 bú kèqi」や「不用谢 bú yòng xiè」が一般的)。これは台湾華語の大きな特徴の一つなので、ぜひ覚えておきましょう。
歹勢 (pháinn-sè) – すみません
pháinn-sè (台湾語発音)
歹勢
すみません / ごめんなさい / ちょっと失礼 (軽い謝罪や呼びかけ)
「歹勢」は台湾語由来の言葉で、「パイセー」に近い発音です。標準中国語の「不好意思 (bù hǎoyìsi)」と同じように、軽い謝罪(人にぶつかった時、道を尋ねる時など)や、ちょっとした頼み事をする際のクッション言葉として、日常的に非常に頻繁に使われます。台湾の街中で最もよく耳にする言葉の一つかもしれません。これが自然に使えると、ぐっとローカルに馴染んだ感じが出ます。

台湾では「晚安」が夜の挨拶として使われることも
時間帯に縛られない!中国大陸でよく使われる挨拶フレーズ
「晚上好」があまり使われないとなると、中国大陸では時間帯に関係なく使える、もっとカジュアルで一般的な挨拶フレーズが重宝されます。親しい間柄から、道でばったり会った時まで、様々な場面で使えるネイティブ感あふれる表現をいくつかご紹介しましょう。
万能選手「你好 (nǐ hǎo)」- でも親しい相手には?
nǐ hǎo
你好
こんにちは
やはり基本中の基本は「你好」です。初対面の人、店員さん、あまり親しくない知人など、相手を選ばず、どんな時間帯でも使える最も無難な挨拶です。しかし前述の通り、親しい友人や家族に対して使うと、少しよそよそしく聞こえてしまうことがあります。親しい間柄では、「你好」の代わりに相手の名前を直接呼んだり、後述する「嗨 (hāi)」や、電話なら「喂 (wèi)」を使ったり、あるいは挨拶なしに本題に入ったりすることも多いです。
若者言葉・ネットスラング由来の挨拶 (哈喽, 嗨)
hā lóu
哈喽
ハロー / やあ
hāi
嗨
ハイ / やあ
「哈喽 (hā lóu)」は英語の “Hello”、「嗨 (hāi)」は “Hi” に由来する、非常にカジュアルな挨拶です。主に若者の間で、友人や同僚など親しい相手に対して使われます。直接会った時だけでなく、WeChatなどのSNSやメッセージアプリでの会話の始めにも頻繁に使われ、気軽でフレンドリーな印象を与えます。ただし、目上の人やフォーマルな場面では避けるべき表現です。
食文化を反映した挨拶「吃饭了吗? (chī fàn le ma?)」
chī fàn le ma?
吃饭了吗?
ご飯食べた? (挨拶として)
これは中国独特の非常に興味深い挨拶表現です。直訳は「ご飯を食べましたか?」ですが、多くの場合、相手の食事状況を本当に尋ねているわけではなく、「こんにちは」「元気?」といったニュアンスの挨拶として使われます。特に中高年以上の世代や、地方などでよく聞かれる表現です。
この挨拶の背景には、「民以食为天 (mín yǐ shí wéi tiān) – 民は食を以て天と為す」ということわざに代表されるように、食べることが何よりも重要とされてきた中国の歴史と文化があります。かつて食糧難の時代が長かった中国では、相手がちゃんと食事をとれているか気遣うことが、最も基本的な思いやりであり、挨拶の言葉となったのです。
もしこの挨拶をされたら、正直に食事の状況を答える必要はなく、「吃了 (chī le) – 食べたよ」や「还没呢 (hái méi ne) – まだだよ」のように軽く答えればOKです。そこから「你呢?(nǐ ne?) – あなたは?」と聞き返したり、別の話題に移ったりするのが自然な流れです。
近況を尋ねる「最近怎么样? (zuìjìn zěnme yàng?)」
zuìjìn zěnme yàng?
最近怎么样?
最近どう?
「最近どうですか?」と相手の近況を尋ねるこのフレーズも、挨拶代わりによく使われます。「你好」の後に続けて「你好,最近怎么样?」のように言うことも多いです。日本語の「最近どう?」と同様に、当たり障りのない会話のきっかけとして便利です。返答としては、「挺好的 (tǐng hǎo de) – 元気だよ」「还行 (hái xíng) – まあまあかな」「老样子 (lǎo yàngzi) – 相変わらずだよ」などがあります。
相手の名前や役職+「好」 (老师好, 李总好)
[名前/役職/呼称] + hǎo
[名前/役職/呼称] + 好
「你好」よりも少しパーソナルで、かつ丁寧さも保てる便利な挨拶が、相手の名前や役職、あるいは呼称に直接「好」をつける言い方です。これは非常に応用範囲が広く、様々な場面で使えます。
- 老师好 (lǎoshī hǎo): 先生、おはようございます/こんにちは/こんばんは
- 李总好 (Lǐ zǒng hǎo): 李社長(総経理)、おはようございます/こんにちは/こんばんは (名字+役職)
- 王经理好 (Wáng jīnglǐ hǎo): 王マネージャー、おはようございます/こんにちは/こんばんは
- 阿姨好 (āyí hǎo): おばさん(年配の女性への敬称)、こんにちは
- 叔叔好 (shūshu hǎo): おじさん(年配の男性への敬称)、こんにちは
- 大家好 (dàjiā hǎo): 皆さん、こんにちは/こんばんは (大勢への挨拶)
- 各位好 (gèwèi hǎo): 皆様、こんにちは/こんばんは (大家好より少し丁寧)
このように、相手に合わせて呼びかけを変えることで、よりスムーズで適切なコミュニケーションが可能になります。特に、先生や上司、年配の方など、敬意を示すべき相手に対しては、「你好」よりも「[敬称] + 好」の方が好まれることが多いです。
久しぶりの再会に「好久不见 (hǎo jiǔ bú jiàn)」
hǎo jiǔ bú jiàn
好久不见
お久しぶりです
しばらく会っていなかった友人や知人と再会した際に使う定番の挨拶です。「好久 (hǎo jiǔ)」は「長い間」、「不见 (bú jiàn)」は「会わない」という意味なので、文字通り「長い間会わなかったね」=「お久しぶり」となります。これは相手の立場や関係性に関わらず使える便利なフレーズです。興味深いことに、英語の “Long time no see.” は、この中国語のフレーズが語源になったという説が有力です。
ばったり会った時の定番「你去哪儿? (nǐ qù nǎr?)」
nǐ qù nǎr? / nǐ gànmá qù?
你去哪儿? / 你干嘛去?
どこ行くの? (挨拶として)
道端やキャンパス内などで、知人にばったり会った時に「你去哪儿? (nǐ qù nǎr?)」あるいは、より口語的な「你干嘛去? (nǐ gànmá qù?)」(干嘛 = 何をする)と声をかけるのも、中国では非常によくある挨拶の形です。これも相手の行き先を詮索しているというよりは、「やあ、どうしたの?」というニュアンスの気軽な声かけです。
聞かれたら、「我去买东西 (wǒ qù mǎi dōngxi) – 買い物に行くんだ」「去上课 (qù shàngkè) – 授業に行くところだよ」「没什么,随便走走 (méi shénme, suíbiàn zǒuzou) – いや別に、ぶらぶらしてるだけだよ」のように答えれば大丈夫です。そこから会話が始まるきっかけにもなります。

カジュアルな挨拶は会話のきっかけになります
中国と台湾:挨拶文化に見る違いと共通点
ここまで見てきたように、中国大陸と台湾では、「こんばんは」の表現をはじめ、いくつかの挨拶や言葉遣いに違いが見られます。しかし、同時に共通する部分も多くあります。最後に、両者の挨拶文化に見られる違いと共通点を整理し、その背景にある文化的な要素について考えてみましょう。
フォーマルとカジュアルの使い分け
中国大陸でも台湾でも、挨拶においては場面や相手に応じた「フォーマルさ」と「カジュアルさ」の使い分けが存在します。「晚上好」や「你好」は比較的フォーマルな場面や、ある程度の距離感がある相手に使われ、「嗨」「哈喽」や名前を呼び捨てにするのはカジュアルな場面や親しい間柄で使われます。この基本的な使い分けの感覚は、両地域で共通していると言えるでしょう。
親しい間柄での距離感の表し方
興味深いのは、親しい間柄においては、丁寧すぎる言葉遣いを避ける傾向が、中国大陸・台湾双方に見られる点です。これは、形式的な礼儀よりも、打ち解けた関係性や「仲間意識」を重視する文化的な背景があるのかもしれません。親しいからこそ、他人行儀な挨拶は不要、という感覚が根底にあるようです。
言葉の裏にある文化的な背景(人情、礼儀)
挨拶の言葉一つ一つにも、その土地の文化や歴史が反映されています。「吃饭了吗?」という挨拶には食を重んじる中国の伝統が、「歹勢」という言葉には台湾社会の温かさや遠慮深さが垣間見えます。また、「晚上好」をあまり使わない背景には、中国的な「人情」を重んじる人間関係のあり方が影響しているかもしれません。
一方で、台湾華語に見られる「晚安」「早安」「不會」といった独自の表現は、普通話からの分岐や、台湾語(閩南語)、あるいは日本統治時代の影響など、台湾独自の歴史的・言語的背景から生まれたものです。これらの違いを知ることは、それぞれの社会や文化をより深く理解する手がかりとなります。
まとめ:状況に合わせて使いこなし、コミュニケーションを円滑に
今回は、中国語と台湾華語における「こんばんは」の表現を中心に、様々な挨拶フレーズとその使い分け、文化的背景について詳しく解説しました。
中国大陸では「晚上好」はフォーマルな場面で使われ、日常会話では稀であること。台湾では「晚安」が「こんばんは」と「おやすみなさい」の両方の意味で使われる可能性があること。そして、両地域ともに、時間帯に縛られず、相手との関係性や状況に応じて使えるカジュアルな挨拶表現が豊富にあることがお分かりいただけたかと思います。
挨拶はコミュニケーションの入り口であり、相手との関係性を築く上で非常に重要な要素です。教科書通りの表現だけでなく、ネイティブが実際に使う自然なフレーズを覚え、TPOに合わせて使い分けることができれば、よりスムーズで円滑なコミュニケーションが可能になります。「吃饭了吗?」のような文化的な背景を持つ挨拶や、台湾の「歹勢」のような地域色豊かな表現を使ってみることも、相手との距離を縮めるきっかけになるでしょう。
今回学んだ知識を活かして、ぜひ実際の会話で様々な挨拶表現を試してみてください。言葉を通じて、中国や台湾の文化、そして人々の温かさに触れることができるはずです。